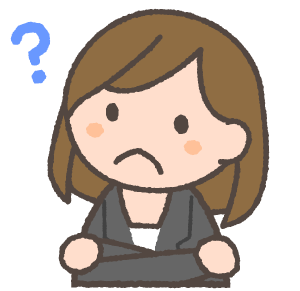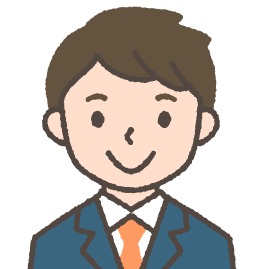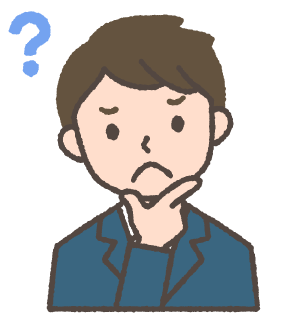今回も過去の判例から労災保険制度について分析してみたいと思います、
今回の事例はA会社とB会社に勤務していた太郎さんが仕事中に心疾患で倒れ死亡したというものです。
近年国も進めているダブルワーク(副業)していた場合の労災の補償内容はどのようになるのでしょうか。
今回の事例は死亡したことに対する遺族補償で争われていますが、負傷して休業した場合の休業補償も同じ考え方をします。
怪我をした方の会社の賃金しか加味しない
結論からいうと、副業していた場合の労災事故の給付には怪我(病気)の原因となった会社の賃金のみで給付日額を算定することになっています。
そもそもなんで労災保険制度ができたかというところに話は及びます。
労災保険は労働基準法から派生している
そもそも、労災保険法は労働基準法から派生してできました。
労働基準法に災害補償の条文があり、労働災害が起きた場合の事業主の最低限の補償義務が定められています。
(療養補償)第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
(休業補償)第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。(障害補償)第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。(休業補償及び障害補償の例外)第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。(遺族補償)第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。(葬祭料)第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
しかし、特に労働者が死亡した場合などは莫大な補償金が発生して事業主が補償金を支払えない可能性もあります。
そのための保険が労災保険です。
労災保険で国が補償することにより、本来事業主が補償するはずのものを肩代わりしているわけですね。
さて、そんな労災保険ですが、そもそも使用者に対する補償義務からできている制度なのでA社での労災事故の補償義務はあくまでもA社にあります。
B社はその労災事故については関係ありませんし、なんの補償義務もありません。
はたして、A社の補償すべき基礎額にBの賃金を含められるでしょうか?
というのがこの問題の本質になります。
現在の法制度では、
A社の労災事故の責任はA社にあり、B社は関係ないのでB社の賃金まで含めてA社は補償する必要はない、だからそこから派生している労災保険もB社の賃金は含めて計算しない。
という結論付けになっています。
生活補償としての労災保険制度
労災保険制度は労災により休業を余儀なくされてしまった方に対する生活の補償という趣旨もありますから、基礎日額の最低保障も定められています。
しかしそれにしても低額なので生活が苦しくなることにかわりはありません。
有識者による検討会などでは、労災保険制度は副業分の賃金も含めて計算するべきである、と答申していますが、今現在そのように法律は改正されていません。
今後働き方改革の一環として、政府は副業を推奨していく方針のようですので法改正もあるかもしれませんね。
判決の結果と現行制度の限界
さて、判例に話を戻すと、今回の監督署の決定は、太郎さんが発症した心疾患は業務によるものである、というものでした、
しかし、補償額の算定にあたって基礎額に副業であるB社の賃金を含めませんでした。
よって遺族が不服を申し立てたわけです。
以前記事で脳・心臓疾患の認定基準を簡単には解説しましたが、発症前の法定外労働時間数が月平均で80時間以上あったかどうかがボーダーラインでした。
監督署はこの認定にかかる労働時間についてはA社の労働時間と副業であるB社の労働時間を合算して業務上であると認定しています。
ここが現在の労災保険制度の法律の限界だと思われます。
法律が現状に合っていないため、上手く当てはめることができないんですね。
判決もちょっとよくわからない内容です。
判決のポイント
- 業務上か否かの判断に監督署がA社とB社の労働時間を合算したことは支持
- 副業で労働時間が少ないB社の業務は今回の疾病の原因とは認められないのでB社の使用者としての責任はない
- だから、今回の労災の原因となった使用者はA社であり、労働基準法による補償の義務があるのもA社である。
- よって、算定基礎額にはA社の賃金のみを含めればよく、B社の賃金を含める必要はない。
- よって監督署の決定は正しい
最後に
現在の法律制度では複数の使用者が連帯して労災の補償義務を負う、ということはあり得ないことになっています。
ですので、労災保険制度もひとつの事故(病気)に対してひとつの会社、ひとつの労災保険番号しか使えないことになっています。
現在の実社会に法律が追い付いていない結果です。
今後、複数の会社で労働するような働き方がスタンダードになってくることは容易に想像できます。
場合によっては、一部業務の請け負いにより報酬を受け取り、一部は会社に雇用され賃金を得る、ということもあり得るかもしれません。
そういった場合に現行の労災保険制度では実態に則した補償をすることはできません。
現在の実社会に合わせた法制度を早急に構築することが求められます。
脳・心臓疾患の認定基準について簡単にまとめた記事です。
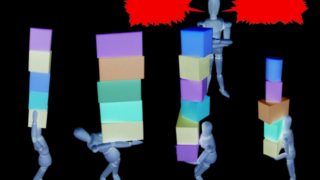
実際に労災が発生した場合にどのような手続きをするべきなのかをまとめました